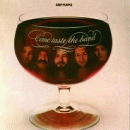変偑宧垽偡傞儈儏乕僕僔儍儞偨偪
俢倕倕倫丂俹倳倰倫倢倕
丂変乆偺悽戙偑儘僢僋懱尡偵偮偄偰岅傞帪丄僨傿乕僾丒僷乕僾儖偼旔偗偰偼捠傟側偄懚嵼偱偁傞丅岲偒偱偁傠偆偲側偐傠偆偲丄乽僗儌乕僋丒僆儞丒僓丒僂僅乕僞乕乿傪堦搙傕僊僞乕偱抏偄偨偙偲偺側偄恖偼偄側偄偲尵偭偰傕偄偄偩傠偆丅偦偆丄僷乕僾儖傪岅傞帪昁偢偲尵偭偰偄偄傎偳丄妝婍傪帩偮偒偭偐偗偑僷乕僾儖偩偭偨丄偲偄偆榖偑弌傞偺偱偁傞丅堦悽戙慜側傜儀儞僠儍乕僘丄屻側傜俛俷冇倂倄偵旵揋偡傞塭嬁椡偑偁偭偨偺偩丅偨偩丄偙偺俀僶儞僪偲傗傗堘偆偺偼丄僊僞乕偺傒側傜偢懠偺妝婍憈幰偵傕塭嬁傪媦傏偟偰偄傞強偩傠偆丅戝曄幐楃側偑傜丄儀儞僠儍乕僘傗俛俷冇倂倄傪挳偄偰偄偒側傝儀乕僗傗僪儔儉傪傗傠偆丄偲巚偭偨恖偼傎偲傫偳偄側偄偩傠偆丅斵傜偼僊僞乕僶儞僪偲偟偰偺僗僞僀儖傪偼偭偒傝帩偭偨僶儞僪偱丄儀乕僗傗僪儔儉偼偁偔傑偱傕榚栶偱偁傞乮埆偄偲尵偭偰傞偺偱偼偁傝傑偣傫乯丅尵偆側傜偽丄偍偄偟偄偲偙偼慡偰僊僞乕偑庴偗帩偭偰偄傞偺偩丅僷乕僾儖偼彮偟堘偆丅妋偐偵丄儕僢僠乕丒僽儔僢僋儌傾偲偄偆傂偲崰僇儕僗儅偩偭偨僊僞儕僗僩偑偄偨偑丄懠偺僷乕僩偵傕廫暘尒偣応偑偁傞壒妝傪傗偭偰偄偨丅偩偐傜丄彮擭偨偪偵傕乽僊僞乕偑傗傝偨偄乿偱偼側偔乽僶儞僪偑傗傝偨偄乿偲巚傢偣傞偙偲偑弌棃偨偺偩丅幚嵺丄儘乕儕儞僌丒僗僩乕儞僘偼杔傕偲偰傕岲偒側僶儞僪偩偑丄挳偄偰傞偲僊僞乕傪抏偔恀帡傪偟偰偟傑偆偺偵懳偟丄僷乕僾儖埥偄偼僣僃僢儁儕儞偺応崌偼偪傖傫偲僪儔儉傪扏偔億乕僘傪偲偭偰偄傞乮尵偄朰傟傑偟偨偑丄杔偼僪儔儅乕偱偡乯丅僷乕僾儖偼丄偄傢偽慡堳偑壴宍偱偁偭偨僶儞僪側偺偩丅俉侽擭戙埲崀偺俫俼乛俫俵偵偍偄偰偼丄僷乕僾儖偼媄弍揑偵偼堦抜掅偄昡壙偺傛偆偩偑丄寛偟偰偦傫側偙偲偼側偄丅偦傟傎偳擄偟偄偙偲傪傗偭偰偄側偄丄偲偄偆偩偗偱壓庤側僶儞僪偱偼側偄丅慺恖偑帺暘偵傕弌棃偦偆丄偲偦偺婥偵側傞偺偼偄偄偑丄偄偞傗偭偰傒傞偲巚偭偨傎偳娙扨偱偼側偄丄偲偄偆偺偑僷乕僾儖偺壒妝側偺偱偁傞丅幚嵺丄杔偼崱帺暘偺僶儞僪偱僷乕僾儖偺嬋傪係嬋偽偐傝傗偭偰偄傞偑丄崱偝傜側偑傜堦嬝撽偱偼偄偐側偄偙偲傪巚偄抦傜偝傟偰偄傞丅傗偭偰傒偰弶傔偰暘偐傞偙偲偱傕偁傞丅偱丄寢榑丄僷乕僾儖偺壒妝偼怺偄偺偩丅僶僇偵偟偰偼偄偗側偄丅
丂廃抦偺捠傝丄悽娫偱偼僨傿乕僾丒僷乕僾儖亖僴乕僪儘僢僋偲偄偆僀儊乕僕偑掕拝偟偰偄傞丅偟偐偟丄嘥婜偐傜嘩婜傑偱儊儞僶乕傕堘偊偽壒妝惈傕堘偄丄捠偟偰挳偔偲僴乕僪儘僢僋偲偄偆僕儍儞儖偩偗偱偼妵傟側偄僶儞僪偱偁傞偙偲傕丄奆偝傫屼懚抦偱偁傠偆丅偙偙偱偼丄僷乕僾儖偲偄偆僶儞僪傪惓偟偔棟夝偟偰栣偆傋偔丄奺帪戙偛偲偺僨傿乕僾丒僷乕僾儖傪夵傔偰怳傝曉偭偰傒傛偆偲巚偆乮拲丗嵞寢惉屻偺俉侽倱僷乕僾儖偼柍帇偟傑偡乯丅
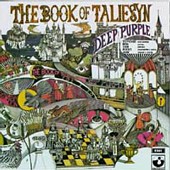
丂丂丂丂丂
戞嘥婜丂丂丂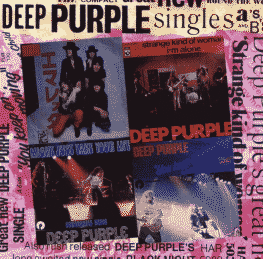
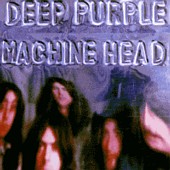
丂丂丂丂丂
戞嘦婜丂丂丂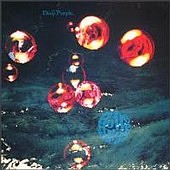
丂偲偼偄偊丄偙偺帪婜恖婥偑崅偄偩偗偁傝丄柤嬋偑懡偔丄傾儖僶儉傕僥儞僔儑儞偑崅偄丅乽僴僀僂僃僀丒僗僞乕乿傗乽僗僺乕僪丒僉儞僌乿傪挳偄偰丄崱偱傕寣偑偨偓偭偰偔傞傛偆側巚偄偵偲傜傢傟傞偺偼丄杔偩偗偱偼側偄偼偢偩丅屄恖揑偵偼乽僂乕儅儞丒僼儘儉丒僩乕僉儑乕乿偲偐乽僱僶乕丒價僼僅傾乿偁偨傝偑岲偒偱偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂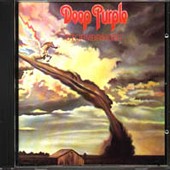 丂丂丂丂丂戞嘨婜
丂丂丂丂丂戞嘨婜
丂戞嘦婜偵亀巼偺徰憸亁偱帋傒偨乬條幃乭偐傜偺扙弌傪丄寢壥揑偵幚峴偟偰偟傑偭偨偺偑偙偺嘨婜偱偁傠偆丅偙偺帪婜偵巆偟偨俀枃偺傾儖僶儉丄亀巼偺墛亁亀棐偺巊幰亁嫟偙傟傑偱捠傝偺僴乕僪儘僢僋偐傜丄僼傽儞僉乕側僥僀僗僩傪壛偊偨嬋傑偱丄僶儔僄僥傿偵晉傫偩岲斦偱偁傞丅僀傾儞丒僊儔儞偺屻姌偲偟偰擖偭偨僨價僢僪丒僇僶乕僨僀儖偼偨偩僔儍僂僩偡傞偩偗偱側偄丄昞尰椡朙偐側儃乕僇儕僗僩偩偑丄嵟弶偐傜僶儞僪懁偼億乕儖丒儘僕儍乕僗偵壛擖傪懪恌偡傞側偳丄僀傾儞丒僊儔儞偲偼堘偆僞僀僾偺儃乕僇儕僗僩傪媮傔偰偄偨傛偆偱丄僴乕僪儘僢僋偐傜偺扙媝傪栚巜偡偵偼傑偢儃乕僇儖偐傜僀儊僠僃儞傪丄偲峫偊偰偄偨偺偩傠偆丅傕偪傠傫戝惓夝丄僇僶乕僨僀儖偺偍偐偘偱僷乕僾儖偼懡嵤側柺傪帩偮僶儞僪偲側偭偨丅傕偪傠傫丄僇僶乕僨僀儖偲僣僀儞儃乕僇儖傪嫞偭偨僌儗儞丒僸儏乕僘偺偙偲傕朰傟偰偼偄偗側偄丅儃乕僇儖傪姺偊傞偙偲偱丄僶儞僪傕曄偊偰偄偭偨僷乕僾儖偼傗偼傝丄杴昐偺條幃僶儞僪偱偼側偄偺偱偁傞丅杔屄恖偺偍慐傔嬋偼乽儐乕丒僉儍儞僩丒僪僁乕丒僀僢僩丒儔僀僩乿偱偁傞丅僼傽儞僉乕側俀恖偺儃乕僇儖傕偄偄偑丄儕僢僠乕偺僶僢僉儞僌偑偁傟丠偲巚傢偣傞丅傜偟偔側偄偗偳丄僇僢僐偄偄丅儕僢僠乕偺堄奜側堦柺傕塎偊傞丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂戞嘩婜丂丂丂丂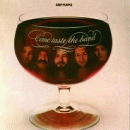
丂僇儕僗儅丒儕僢僠乕偺敳偗偨寠傪丄僩儈乕丒儃乕儕儞偼偁偭偝傝偲杽傔丄彯偐偮儕僢僠乕偵偼弌棃側偐偭偨偱偁傠偆怴偟偄姶妎傪僷乕僾儖偵傕偨傜偟偨丅嘩婜偱偼堦枃偟偐嶌傜傟側偐偭偨亀僇儉丒僥僀僗僩丒僓丒僶儞僪亁偼丄懡嵤側儕僘儉偵枮偪偨柤斦偱偁傞丅僷乕僾儖偼慡偔堘偆僶儞僪偵惗傑傟曄傢偭偨偲尵偭偰偄偄偩傠偆丅屻擭丄僀僄僗偵僩儗僶乕丒儔價儞偑傕偨傜偟偨偺偲摨偠岠壥傪儃乕儕儞偼僷乕僾儖偵梌偊偨偺偩丅堦枃偩偗側傫偰丄杮摉偵惿偟偄丄偙偺傑傑懕偗偰梸偟偐偭偨丅偲偼偄偊丄僷乕僾儖偺柤慜偼巆偭偰傞栿偱丄儃乕儕儞偼僣傾乕偱乽僗儌乕僋丒僆儞丒僓丒僂僅乕僞乕乿摍傪憡曄傢傜偢抏偐偝傟傞偺偑丄寵偱偨傑傜側偐偭偨傜偟偄丅偦傝傖偦偆偩傠偆側丅偱傕丄僼傽儞偼梫媮偡傞偟丄惓偵斅嫴傒丅帿傔偨偔傕側傞偩傠偆丅儊僕儍乕側僶儞僪偵壛擖偡傞偺偼杮摉偵妎屽偑偄傞偙偲側偺偩側偁丄偲幚姶偟偨丅偱傕偲偵偐偔丄偙偺傾儖僶儉昁挳偱偡丅僷乕僾儖寵偄偱傕丄挳偄偰壓偝偄丅
丂偲丄挿乆偲僷乕僾儖偵偮偄偰岅偭偰偒偨偑丄扨偵條幃宯俫俼偺尦慶偲偄偆偩偗偱側偄丄僨傿乕僾丒僷乕僾儖傪傕偭偲昡壙偟偰梸偟偄偲巚偆丅傕偪傠傫丄俉侽擭戙埲崀偵搊応偟偨條幃宯僶儞僪傛傝僷乕僾儖偺曽偑偼傞偐偵僇僢僐偄偄偺偼帠幚側偺偩偑丅偪側傒偵丄杔偵偲偭偰偼崱偱傕堦斣岲偒側僪儔儅乕偺堦恖偼僀傾儞丒儁僀僗偱偁傞丅
丂僨傿乕僾丒僷乕僾儖偼尰嵼偱傕妶摦拞偩丅僗僥傿乕僽丒儌乕僘偲偄偆庒偄僊僞儕僗僩偑婃挘偭偰偄傞傜偟偄丅偟偐偟丄偦偺俋侽倱僷乕僾儖傪杔偼堦搙傕挳偄偨偙偲偑側偄丅惓捈尵偆偲晐偄偺偩丅偮傑傫側偐偭偨傜偳偆偟傛偆丄偲巚偭偰偟傑偆偺偱偁傞丅傕偟丄崱偺僷乕僾儖偑偮傑傫側偄僶儞僪偩偭偨傜丄杮摉偵愄偺柤慜偺傒偱惗妶偟偰偄傞夁嫀偺堚暔偵側偭偰偟傑偆偺偱偼丅杔偼偦傟傪嫲傟偰偄傞丅僨傿乕僾丒僷乕僾儖偼偄偮傑偱傕丄僇僢僐偄偄尰栶偱偄偰梸偟偄偺偩丅偱傕丄偦傟偼柍棟側朷傒偩傠偆偐丅
俶俷俿俤丂俀侽侽侽丏俀丏俆
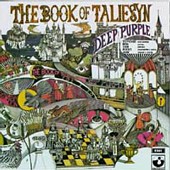 丂丂丂丂丂戞嘥婜丂丂丂
丂丂丂丂丂戞嘥婜丂丂丂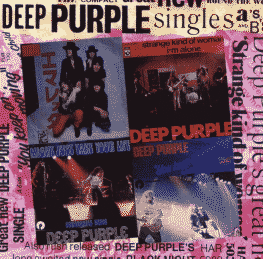
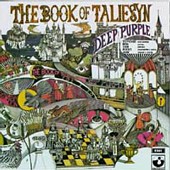 丂丂丂丂丂戞嘥婜丂丂丂
丂丂丂丂丂戞嘥婜丂丂丂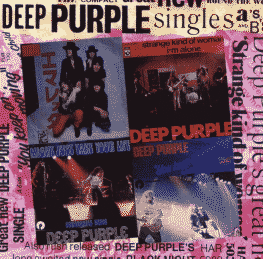
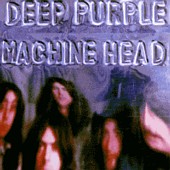 丂丂丂丂丂戞嘦婜丂丂丂
丂丂丂丂丂戞嘦婜丂丂丂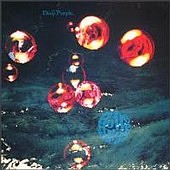
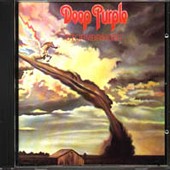 丂丂丂丂丂戞嘨婜
丂丂丂丂丂戞嘨婜